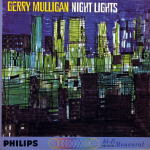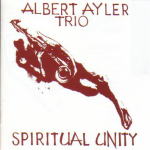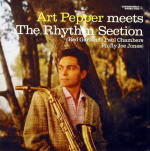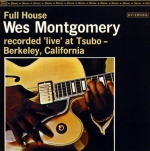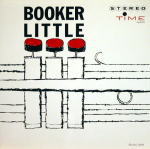SONNY ROLLINS (ts) PHIL WOODS (as) J.J.JOHNSON (tb) ROGER KELLAWAY (p) KENNY BURRELL (g) WALTER BOOKER (b) FRANKIE DUNLOP (ds) ETC OLIVER NELSON (arr, conductor) * 1966. 1.28 |
RCAからIMPULSEへ移籍後の第二弾(リアルタイムで)、人気作。 初めて‘‘Alfie’を聴いたのは、まだ、ジャズを聴き始める前、自動車教習所のスクールバスのラジオから。ロリンズの名は聞いた事はあるが、演奏を聴くのは初めてだった。 後から分かったのですが、‘Alfie’のショート・ヴァージョンの方で、音とフレーズがどことなくデフォルメされたロリンズのプレイが実に新鮮でカッコよかった。 本作は映画音楽のイメージが強いカヴァで随分損をしているけれど、実際は、スタジオで錚々たるメンバーをバックに配し、O・ネルソンのペンでしっかり作り込まれていており、したり顔で「所詮、映画音楽」とか、「ノリの良い‘Alfie’一発」とか、ネガティヴに捉える方が居られますが、変な色眼鏡を掛けて聴く必要はない。 ただ、来日公演で‘Alfie’やカリプソ・ナンバーを演り出すと、聴衆が立ち上り、手拍子と共にバカ騒ぎをし出しすあたり、ホトホト興醒めしてしまう。 それはそれとして、ロリンズはもとより、サイドのバレル、キャラウェイのソロも良いし、ダンロップの小気味いいドラミングも聴きもの。斬新さはないけれど、ソリストを絞り込んだネルソンのアレンジがGooです。 全6曲中、ロリンズのtsが如何に素晴らしいか、如実に語っているナンバーが、実は、ほとんどの方がノーマークしているA-2、‘He Is Younger Than You Are’。 中年男の悲哀を情感を込め、心模様をデリケートに吹き綴るロリンズ、お見事! ロリンズ自身も会心の出来だったのだろう、最後の一音をtsではなく肉声で締め括っている。 「テナー・タイタン」という異名を欲しいままにした50年代後半を愛するあまり、60年代のロリンズに?マークを付けているファンも少なくないけれど、‘He Is Younger Than You Are’で聴かせる繊細にして奥深いプレイにもう一度耳を傾けては如何でしょうか。 例えば、コルトレーンのバラード・プレイはストレートな上、リリシズムをも湛えているので、割と万人に受け容れ易く、反面、ロリンズにはリリシズムという要素はないが、そうしたシンプルな一言では言い表せないサムシングを含み、一筋縄ではいかない。。こうした両者の特徴は、コルトレーンのコピーは掃いて捨てるほど輩出した一方、ロリンズをコピーしたプレイヤーは殆どいなかった、否、できなかった事と無関係ではありません。 数多くのヒット作、当時の問題作が宿命とも言える「時の審判」に退色するの中で、この作品は、些かもその光を鈍らせる事なく、むしろその存在感を増していると思う。少なくとも自分には。 余談を・・・・・・ 4ヵ月後、ロリンズは、スモール・コンボで3作目の‘EAST BROADWAY RUN DOWN’を吹き込む。しかし、親会社ABCの担当重役から「こんなこんなアルバムを作るもんだから、売れないんだ!」と激しく叱責され、自尊心をズタズタに破られたロリンズは、その後、レコーディングを拒み続けたという。 |