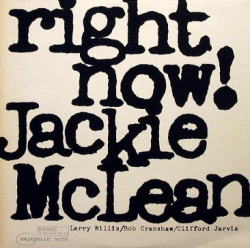
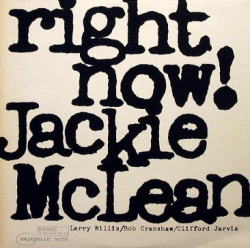

BLUE NOTE BST 84215
JACKIE McLEAN (as) LARRY WILLIS (p) BOB CRANSHAW (b) CLIFFORD JARVIS (ds)
1965
また一人「モダン・ジャズ黄金時代」の生き証人が天に召された。享年、73歳という。
自分の歳を顧みず、もうそんな歳だったのかと改めて思い知らされた。だが、僕の頭の中には、いつ、いかなる時でも‘あの頃’のマクリーンしか存在しない。
京都、四条河原町を南座、八坂神社方面へ向かう途中、四条大橋の手前に高瀬川に架かる四条小橋という忘れられたかのような小さな橋がある。川に沿ってちょっと上がった所にその昔、「ダウンビート」があった。うなぎの寝床のように細長く、左サイドにバー・カウンターが奥まで続き、場所柄からしてジャズ喫茶というよりジャズ・バーと言った雰囲気であった。
まだジャズを聴き始めて間もない頃、初めてそこを訪れた時、入口のすぐ左の新譜コーナーに本作が飾ってあり、‘LET FREEDOM RING’の演奏に衝撃を受けていたばかりの僕は躊躇することなくリクエストした。イントロなしにいきなり、asとは思えぬ迫力あるトーンで吹き始めるマクリーンにまたしても強烈なパンチを喰らった。必死にマクリーンのソロを追いかけているうち、まるで自分が灼熱の砂漠をラクダに乗って先陣をきって疾走する「アラビアのロレンス」にでもなったかのような高揚した爽快感に包まれ、二曲目がどんな演奏だったか全く記憶がなかった。まぁ、とにかく、ファイティング・スピリットの塊のようなマクリーンのasに圧倒されたのだ。
ダウンビートに行くと本作を必ずリクエストしたものだが、この店ではもう既にリクエスト上位の一枚であった。
本作はマクリーンの数ある作品の中でも異色の意欲作である。ワンホーン・カルテットに加えA面、B面、各2曲で構成されている。重量感あるtsでもこうした構成は極めて例が少ない。それほど、本作の充実度、テンションは高い。しかし、僕の思い過ごしかもしれないが、巷では冷遇されたいるようだ。相変わらず、「センチメンタル・ジャーニー」をはじめとするプレステージ、或いはBNの初期の時代、所謂「ハード・バップ」ジャッキーに人気が集まっているようだが、それなら、いっそ、初リーダー作、アドリブ盤(通称、ネコ)のパーカー丸写しながら、ハツラツとしたプレイの方が好感が持てるし、そう思っているファンも結構多い。
だが、マクリーンの音楽的ピークは好むと好まざると間違いなく、この時期、つまり‘LET
FREEDOM RING’から始まる「アグレッシヴ・ジャッキー」なのだ。
確かに、本作の2曲目‘Poor Eric’では、人気の秘密とも言える「青春の甘酸っぱさ」など微塵もなく実にクールだ。でも、深く掘り下げられた叙情性はかってないほど表現力を増している。また、B面では、コールマン、コルトレーンの影響がモロに出ている部分が垣間見えるが、「変わらずして変わる」といった矛盾を背負いながらも、果敢に攻め切るその姿勢は、聴く者、全ての胸に響いてくるはずだ。
‘DEMON'S DANCE’(1967年)を最後にまるで疲れ果てたようにその後、数年間、ジャズ・シーンの表舞台から身を退いた事自体が、当時のマクリーンの演奏密度の高さを裏返しに証明している。「闘争」とも言える「自己革新」に果たして自分なりの答を見い出せたのか、どうかはともかく、こうしたジャズ・マンが「モダン・ジャズ黄金時代」を支えていた事実は永久に残るであろう。 あぁ、合掌。
ps 本作でおもしろい話があります。それは、マクリーンのasの「音」である。asとは思えぬ迫力に驚いた僕は、あるジャズの先輩に話をしたところ、本作の1st盤ジャケットでも最初、tsと間違えて印刷し、後からasに修正した跡が残っている、と答えた。
本作は1966年11月にリリースされており、僕が所有する盤は「NEW YORK盤」、インナー・スリーヴは「1939-1966 27 YEARS」なので、限りなくオリジナルに近い?と思うが、修正した痕跡はない。この話は本当なのだろうか? 今まで「その跡」を見たことがありませんが。
(2006.4.13)

EPIC LN 3436
PHIL WOODS (as) BOB CORWIN (p) SONNY DALLAS (b) NICK STABULAS (ds)
1957
瀬戸大橋が開通(1988年4月10日)して間もない初夏、倉敷に仕事の関係で出張に出かけることになった。正確に言えば、倉敷の一つか二つ大阪よりの「川崎医科大学、付属病院」であったが、折角なので「瀬戸大橋」を渡ってみようと一泊を入れた。泊まりは倉敷の「アイビー・スクェア」とし、早めに夕食を済ませ、「ジャズ喫茶」探しを始めた。
別に当てがあった訳ではないが、こういう町に一軒ぐらいあっても不思議ではないという確信めいたものだけが頼りであった。探し始めてすぐ例の観光スポットから一、二筋、路地に入った所に運良く「ジャズ茶房」を見つけた。我ながらその嗅覚に驚いた。角を右に回るか左に回るかで結末はまるで違っていただろうに。店の名は残念ながら失念したが、外観は町並みの景観に合わせた和風だが、中はウィンザー調の椅子やテーブルでまとめられ、こざっぱりした感じの趣味の良い店で、嬉しいことにバー・カウンターまで設置されていた。
早速、カウンターに腰を下ろすと、奥から「いらっしゃいませ」と女性が現れた。旅先のジャズ喫茶で女性とは、なかなかオツなものである。他の客は誰もいないし(別に関係ないかぁ)。
で、最初は、「何処から?、何しに?」なんてたわいの無い話をしていたところ、突然、「コルトレーンは好きですか?」ときり出してきた。
「イエス or ノー」の返事では、話の成り行きが限定されると考え、ここは「ええ、聴きますよ」とかわした。すると「何をよく聴きますか?」と訊ねてきたので「クレッセントかなー」と言うと、彼女の眼の奥がキラリと光った。想定外の返事だったのだろう。マイ・フェイバリット・シングスとかバラードを想定していたのかもしれないし、あまり知名度の高くない名が出たからだろう。
しばらくして今度は「どのレコードが一番、良いでしょうかね?」と聞いてきたので「トランジション」と答えると、予想外の名に好奇心の炎が眼にメラメラと燃え上がるのがはっきりと映し出されていた。もう、それからは「コルトレーン談義」で盛り上がったが、彼女もやはり、後期コルトレーンを苦手としている一人で、所謂マイ・フェイバリット・シングス、バラード止まりであった。そこで、「ジャイアント・ステップス、クレッセント、トランジション」の三枚をもう一度、既成概念を棄てて聴くことをお薦めした(大きなお世話だったかもしれませんが)。


彼女の好きなクリスの一枚
では、本題に入ろう。その前に、本レコードは70年代中期?に1,300円シリーズで発売された国内盤。オリジナル盤と聴き比べたワケではないが、「音」はイイ。少なくともウッズの若々しく張りがあってしかも艶のあるasの音色は申し分ありません。だだ、リズム・セクションがやや後方に控えている点がオリジナル盤と異なっているかもしれません。
ウッズにとって本作は50年代最後となる作品で、その後、キャンディド(1961年)、インパルス(1966年)に散発的にリーダー作を発表しているものの1968年にあの‘ALIVE
AND WELL IN PARIS’で劇的にカンバックするまで長い「暗黒時代」を迎えることになる。
この作品はタイトル、アルバム・カヴァで象徴されるような「リラクゼーション」、「和み」以上に僕はエモーション、それも「秘めたるエモーション」を強烈に感ずる。その端的な演奏が‘Easy Living’。とても「気ままな生活」なんて生温いものではなく、ウッズそのもの、エモーションの塊のようだ。その証拠に、pにソロを取らせず一気に最後まで吹き通している。ここがこの演奏のみならず本作のキー・ポイントと思う。続く‘I Love You’も語り口がとても情熱的だ。また、本作でも‘YOUNG BLOODS’同様に愛妻のために作曲している。僕だってできる事なら、そうして家内に捧げたい。
ps あの倉敷の「ジャズ茶房」はまだ、健在なのだろうか?そして彼女はどうしているのだろう? このレコードを聴く度に思い出す。
(2006.11.2)

POLYDOR 583 734
JOHNNY GRIFFIN (ts) KENNY DREW (p) NIELS HENNING ORSTED PEDERSEN (b)
ALBERT HEATH (ds)
1967. 3. 30〜31
前回、UPしたモンクの‘SOMETHING IN BLUE’の中で触れた‘THE MAN I LOVE’でも、モンクではなく、目移りして手に入れたグリフィンのレコードがコレ。
彼は勿論、時代の先駆者でなければ、ロリンズ、コルトレーンやゲッツ等の大物でもないけれど意外に「街の人気者」である。しかも頑固なハード・パッパーである。多くのハード・バッパー達が60年代後半から70年代にかけて失墜していくなか、63年、いち早くに渡欧して78年に帰国するまでヨーロッパを活動の拠点とした点、D・ゴードンと酷似している。
渡欧した者が全て成功したかと言えば、同じtsのモブレーの例を出すまでもなく必ずしもそうでもないのも事実。ヨーロッパの風土に適応できるか、どうかと言った単純な物差しでは推し測れぬsomethingがあるやもしれません。
その秘密を解くカギが本作。コペンハーゲンのクラブ「モンマルトル」でのライブ盤。グリフィンはライブ・パフォーマンスの術を心憎いほど熟知している。変幻自在にして縦横無尽にtsを鳴らし、しかも繊細だ。つまり、聴衆を飽きさせることが無い。例えば、トップの‘The
Man I Love’では豪快な中にもデリケートな面も窺わせ、続く十八番、‘Hush-a-bye’はまず、ドリューにたっぷりとソロ・スペースを与えながら自分の出番をじっくりと待ち構え、思わせぶりにペデルセンとのデュオから入り、ヒース、ドリューと徐々に絡んでいくシチュエーションは実に緻密です。
でも、本作の最高の聴きものは人気の‘Hush-a-bye’ではなく、B面の一曲目のオリジナル・ナンバー‘Blues For HARVEY’。次第に燃え上がっていくグリフィンのtsにいつの間にかこの上ない快感を覚えてしまう。この演奏を聴くと、グリフィンはヨーロッパで成長、腕をあげたなぁ、と思わずにはいられない。
‘Sophisticated Lady’では、一転、短いながらもしっとり歌い上げる。ただ、ラストの「早撃ち、ジョニー」‘Wee’は苦手だ。
なお、リズム・セクションでは、手癖フレーズの乱発に目をつぶれば、それなりに好演のドリューよりも、悠然とスケールの大きいbを聴かせるペデルセンの存在が大きい。
本作は、円熟味を増したグリフィンの魅力を記した最良のライブ・アルバムではないでしょうか。
(2007.3.27)