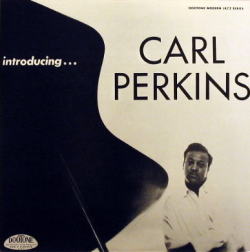
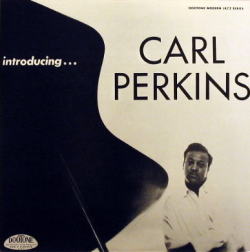
INTRODUCING / CARL PERKINS
DOOTONE DTL 211
CARL PERKINS (p) LEROY VINNEGAR (b) LAWRENCE MARABLE (ds)
1955、1956
別にツウぶるワケではないが、「ジャズ・ピアノ」と言うと直ぐB・エバンスを口にし、それも‘WALTZ
FOR DEBBY’が好きと言う人の話は、あまり信用しない。加えて言うならば、‘KIND
OF BLUE’、‘BALLADS’も然りである。へそ曲がりなのだろう。
その代わり、‘SAN FRANCISCO SUITE / FREDDIE REDD’や本作が好きと言う人の話は無条件で信用してしまう。それほどに本作は十本の指に入るぐらい好きなピアノ・トリオ・アルバム。パーキンスはW・コーストでいろいろなセッションに参加し、地味ながら、これからという29歳の時、自動車事故で夭折した黒人ピアニスト。
どこが良いかと聞かれても、スインギーで歯切れのいいピアノ・タッチとパーキンスのオリジナルからスタンダードを含め、最後まで聴き飽きない絶妙な曲の配列かなぁ、てな具合で偉そうな事を言ったわりにはまことに低レベルの理由である。まぁ、好き嫌いなんてものは、所詮、低いレベルで語られるケースが多い。
さて、本作は、パーキンスがマイナー・レーベルに残した唯一のリーダー作。左手のハンディを全く感じさせないソロ・ワークは煌びやかなトーンと、趣味の良いスイング感と相俟って独自の世界を創り出し、「隠れた人気盤」でもある。バラード曲でのともすればオーバー・デコレイティヴな表現方法も身体的ハンディを克服したプライドの表れと好意的に解釈している。
そんな中、特に好きな演奏はガレスピーの‘Woody'n You’、スタンダードの‘It
Could Happen To You’。トドメはラスト・ナンバー、パーキンスのオリジナル‘Carl's Blues’。
指を鳴らし、エモーショナルなブルース・フィーリングに酔え!
ps パーキンスは同じ「DOOTONE」レーベルで‘DEXTER BLOWS HOT AND COOL’(DLP 207)に参加しており、世評の割りに今ひとつ調子の上がらぬデックスをアシストしている(否、し過ぎかもしれない)。
(2006.1.22)

HEART NOTE HN 004
MILES DAVIS (tp) WAYNE SHORTER (ts) HERBIE HANCOCK (p) RON CARTER (b)
TONY WILLIAMS (ds)
1964. 10. 1
‘IN BERLIN’の1週間後のブートレグ。‘IN BERLIN’は録音から数年経ってからリリースされたが、れっきとした公式盤。ジャケットもタキシードを着ている。方や本作は、ズバリ盗用、ブート丸出しです。演奏も本作の方がラフ?ぽい、しかも「音」はプア。だけど、僕は何故かこのブートの方が好きなんです。
収録曲は一曲だけ異なる。‘IN BERLIN’が‘Milestone’でスタートするのに対し、本作は‘Stella
By Starlight’で始まり、その後は、順序は変わるが同じ曲が続く。この出だしがミソかもしれない。ミュートではなくオープンで、スローで入りすぐテンポを上げ、またスローに戻すマイルスの自在なペットが分かっていても聴きもの。二度ほど、音を外しているが、ライヴらしくて逆にいい。
‘Autumn Lieves’は意外にもアップ・テンポで入り、それこそテーマをバラバラに解体し、新しい‘Autumn
Leaves’を創造していく展開が何とも新鮮です。但し、ショーターにスタンダードは鬼門、「枯葉」が「病葉(わくらば)」になってしまう。
しかし何といっても、本作のハイライトは、ラストの‘So What’。
まさに亀田兄弟である。どちらが兄で弟かはともかく、マイルスとショーターの、特にマイルスの狂ったようなブローには、裸足で逃げ出すより手がなさそうです。恐れ入りました。参りました。マイルスもショーターも当時30代、身も心も燃えてますねー。ヤッパー、「あの頃のモダン・ジャズ」が最高なんでしょうか?
LPの収録時間の関係かどうか解りませんが、ハンコックのソロの途中でフェード・アウトしており、その後の結末を知りたいもの。その点、CDはこれをクリアしているはずなので、本作を聴くならCDの方がいいかもしれません(未聴です)。
(2006. 5. 9)


JAZZLAND JLP 945S
DON SLEET (tp) JIMMY HEATH (ts) WYNTON KELLY (p) RON CARTER (b)
JIMMY COBB (ds)
1961.3.16
リーダーは超マイナーだが、リズム・セクションは超メジャー級。ジャズランドを含めリヴァーサイド(系)はこうした穴盤が多くなかなか奥の深いレーベルです。
スリートと言えばPJレーベルの‘AND THE 4 SOULS / LENNY McBROWNE’がマニア好みの同じ穴盤として知られていて、同作でのスリートのtpは好録音により、真にハリのある音色で印象深いプレイを聴かせてくれています。
で、本作ではどうか?というとちょっとイメージが違う。レーベルの音の違いかもしれないが、‘White’、つまり、ジャケットの伊達男ぶりのようにいかにも「白人」らしいジェントルさ、スマートさが全面に浮き出ており、他の四人(Negroes)の黒さとのコントラストが本作の一つ狙いと言えるだろう。
スリートのtpはマイルス、ドーハム、そしてミッチェルからも影響を受けている、とライナーノーツで
I ・ギドラーがコメントしている通りですが、結構、オリジナリティに富んだフレーズを吹くあたり、実力もかなりある。
スリートは1938年、インディアナ州 フォート・ウェイン生れ。1938年と言えば、そう、リトル、ハバード、モーガンの3人のtp神童が生れた同じ年。スリートのtpは「あく」が無いだけに巡りあわせがあまりにも悪すぎたようだ。
さて、収録曲は‘Secret Love’、‘Softly As In A Morning Sunrise’、‘But
Beautiful’のスタンダード三曲、スリート、ヒースのオリジナルが各一曲、そしてクリフォード・ジョーダンのオリジナルが二曲と構成もバラエティに富んでいる。
そんな中、‘But Beautiful’のバラードも良いが、ジャーダン作のバリバリのハード・バップ曲、‘Brooklyn
Bridge’と‘The Hearing’の出来が良く、意外な側面が覗かれる。
共演者では、pのケリーが抜群にイイ。この頃のケリーは何を聴いても素晴らしいが、本作のケリーはスリートに合わせ、「黒さ」を適度に控えたプレイが出色の出来。‘But Beautiful’で小気味の良いソロの途中、百年の恋もぶち壊すような無粋なテナーで「オレの出番だ」とばかりしゃしゃり出てくるヒースを聴くと「お前、引っ込んでろ」と言いたくなるほどです。
また、当時、マイルス・グループの仲間のコブと息の合ったところを見せ、ラスト・ナンバー‘The
Hearing’でのファンキーさを押さえたソロも極上、ホントいいなぁ、ケリーって。
本作は、所謂‘How To’もの、つまりガイド・ブックにはまず紹介されない一枚。「早道」か?「道草」か?それは聴き手の自由。されどいずれジャズに「早道」など存在しないことを悟るだろう。
一度、スリート、唯一のリーダー作で「道草」をしてみませんか。ジャズは「学問」でも、ましてや「哲学」じゃ、ないんだから。
(2006.7.3)

STEEPLECHASE SCC-6011
KENNY DORHSM(tp) ROLF ERICSON (tp flh) TETE MONTOLIU(p)
NILES-HENNIG ORSTED PEDERSEN(b) ALEX RIEL(ds)
1963. 12. 5
本作はご承知の通り、ステープルチェイスが新録したものではなく、その音源を買い取り、リリースした‘Classics’シリーズの一枚。ドーハムものではもう一枚‘SHORT
STORY’がある。録音場所は同じコペンハーゲンのクラブ‘モンマルトル’。リズム・セクションはお馴染みのハウス
トリオで相方がエリクソンとボチィンスキーと入れ替わります。
2週間後に録音された‘SHORT STORY’(6010)の方が先に(1979年)に日の目を見、本作は翌1980年に発表されている。
そうした経緯からなのか、フロントカヴァのイメージからかもしれませんが、‘SHORT
STORY’はそれなりに良く知られ、ドーハムの裏名盤とも言われる一方、この‘SCANDIA
SKIES’はまるで月見草のようにひっそりとした存在です。

KENNY DORHSM(tp) ALLAN BOTSHINSY(flh)
TETE MONTOLIU(p)NILES-HENNIG ORSTED PEDERSEN(b)
ALEX RIEL(ds)
両者の出来自体はほぼ互角、甲乙付け難く、なかなか充実したライブが楽しめます。強いて優劣を付けるとするとほんの僅かな差で‘SHORT
STORY’の方が上かもしれない。
でも、僕の好みは本作‘SCANDIA SKIES’の方が遥かに上になる。
まず、演奏には関係ないが、カヴァについては、カッコ付け過ぎの‘SHORT STORY’よりあまりにも写実的過ぎのきらいもある本作に好感が持て、また、エリクソンと和やかに軽食を楽しんでいるリアのワンショットもなんだか微笑ましい。
で、演奏は、どうかと言うと、もう好みの領域と言うしかありません。ドーハム個人のプレイはどちらも好調ですが、僕は‘SHORT
STORY’の‘Bye Bye Blackbird’に於けるテテのpが苦手なんです。それと、‘The
Touch Of Your Lips’でフューチャーされたボチンスキーのflhが素晴らし過ぎてドーハムを喰っている。うっかりしていると、ドーハムと聴き間違えてしまいそうです(タコ耳ですので)。
その点、本作のB面のトップ、タイトル曲にもなっているオリジナル‘SCANDIA
SKIES’のドーハムならではの情緒纏綿としたプレイにグッと惹かれる。
また、両方に入っているボンファの名作‘Manha De Carnival’もテーマの後、直ぐフォー・ビートに切り替えたソロもナイスですね。
そして、ラスト曲‘It Could Happen To You’が途中でフェード・アウトしてしまい、残念ですが、もし、完結されていたならば、両者の立場は逆転していたでしょう。惜しい。
いずれにしても、この2枚は63年、好調時のドーハムの姿をナチュラルに記録した作品として大いに価値があると思います。
なお、「音」に関してはこの手のアルバムとして全く問題ありませんので、ご心配なく。レーベルにはステレオと表示されていますが、
ほぼモノラルに聴こえます。
(2009.3.22)