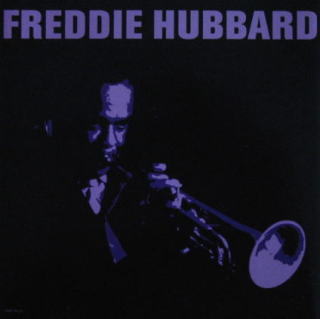
THE ARTISTRY OF
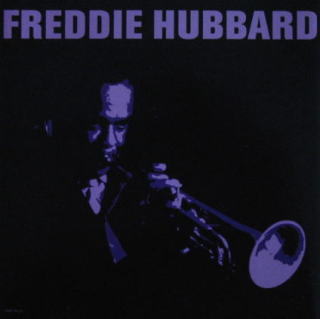




FREDDIE HUBBARD live at NAGOYA Blue Note, 9/10/2003
ハバードが‘The New Jazz Composers Octet’を率いたライヴ。メンバーは2年前、久しぶりにリリースした「NEW
COLORS」とほぼ同じで、bsだけ違っている。‘NAGOYA Blue Note’の中に入るのは初めてでしたが、こんなに広くてキレイとは思いませんでした。
本場‘NEW YORK Blue Note’より遥かにグレードが高い。
開場時間よりも早く着いたので、近くの廃盤屋へ寄るついでに店の前に行った。
そして、愕然とした。
‘Tonight’の案内を見て驚いた。‘The New Jazz Composers Octet’だけでハバードの名も顔もありません。しかもミュージック・フィーが4,000円(8,000円のところ)になっているではないか。イヤな予感が脳裏を走った。そしてその予感が当たってしまったのだ。
リップ・コンディション不調のため、ハバード抜きでの措置でした。
キャンセルして全額返金か、半額返金で‘The New Jazz Composers Octet’を聴くかの説明があり、当然、後者を選びました。係り員に尋ねても詳細は解らなかっが、僕は必ずハバードは顔を出す、と確信していました。
涙してしまった。
6:30過ぎ、チック・コリアの‘Inner Space’から演奏が始まる。ハバードの姿は無い。スピーディで重量感溢れるサウンドはCD(NEW COLORSに収録)を遥かに超え、正に‘モダン・ジャズ’そのものだ。レトロな感じは微塵もありません。スリルに満ちたD・Weiss(tp、実質上のリーダー)のアレンジが素晴らしい。2曲目は何かで聴いた記憶のある曲ですが、タイトルを思い出せない。途中、Weissがステージの袖へ行き誰かと話しをしている。ハバードと直感しました。
3曲目は代表作の‘One Of Another Kind’。テーマの途中、やはりハバードがflhを片手に出てきた。しかし、音が、フレーズが続かない。顔を赤くして懸命し吹く。痛々しい。でも、ハバードは吹く事を止めない。心配そうにメンバーがババードを眺めている。僕は、もう止めてくれ、と心の中で叫んだ。
この一曲でハバードはもうステージから下がると思ったが、次の'Blue Spirits’が始まると、時々目を天井に遣りながら、腕を振って静かにリズムを取っている。本当にイイ曲だ。若かりし頃を思い出したのだろう、今度は先頭でソロを取り出したのである。しかし、思うようにflhは鳴ってくれない。もどかしい。何度もトライするハバードに思わず目じりから涙が零れた。
Weissは、まるで父親を心配する息子のように片時も目をハバードから離さない。C・ハンディのssのソロも会心の出来でハバードと目を合わせお互いに頷いていた。レコード(CD)では、絶対にあり得ない名演でした。最後の‘Blues For Miles’では即興?のボーカルとジョークを交えた語りで会場をアット・ホームな雰囲気にして締め括る。
アンコールはありませんでした。その代わり、ハバードがマイクで観客とちょっとしたトーキングをしました。英語なのでよく解りませんが、どうも大阪での演奏(6
& 7日)で傷めたようです(違っているかもしれません)。何度も手を合せて日本語で「ごめんなさい」と繰り返していました。
その時もWeissはずっとハバードの傍から離れなかった。全員がハバードを敬愛しているのだろう。
それに、この‘The New Jazz Composers Octet’自体の演奏は一級品です。
* 最後に、観客誰一人として、この日(ファースト・ステージ)の演奏に不満を漏らす様子の無かったことを付け加えておこう。
30年前の思い出
1972 or 3年の秋と思いますが、ハバードがクインテットを率いて来日した。京都の三条河原町にある‘?beat’(僕が京都を離れてからオープンしたので名前を失念しました)というジャズ喫茶へ来ると言うので馳せ参じた。まだ、スーパー・スターへの途上中とはいえ、まぁ、よくこんな所(失礼!)来たものだと、驚いたものでした。
当時の人気曲‘First Light’(74年のグラミー賞を獲得したレコード)から始まり、バリバリのtpを聴かせてくれました。狭く超満員のため、ハバードの顔から、すぐに汗が噴出し、係り員に拭くものをさかんにリクエストしていたが、英語が解らずまごついていたので、偶然、持っていたハンド・タオルをハバードに渡した。その時、チョットした言葉も交わしました。だから、演奏後、サインを貰う際、覚えてくれていたので、、メンバー全員でバッグのキャンバス地に心よく書いてくれました。
Love
Freddie Hubbard
Peace + Love
George Cables
Phil Wrighit?(マネージャー?)
レニー・ホワイト
Lenny White
Junior Cook
Rufus Reid (縦書)
ハバード、35、6才の上り坂の時。凄かった。店では、オープン・リールを回していたが、そのテープは今、何処の誰の手にあるのだろう。
休憩中、Cookはフルートを、ホワイトはdsの練習をずっと真面目にしていました。ボスの仕付けがいいのでしょう。
皆、若かった。特にL・ホワイトはナイーブな少年みたいで、確か20才を少し超えた位ではなかったでしょうか。
演奏後、彼らは斜め前のヤキトリ屋へ入っていきました。その後の京都の夜はどうだっのだろう?
* 上から
僕の宝物
vol.1
vol.2
* 家に帰って‘Blue Spirits’を聴き、また、涙がこみあげてきた。
(2003/10/11)
vol.3
BLUE NOTE BST 84056
FREDDIE HUBBARD (tp) HANK MOBLY (ts) McCOY TYNER (p)
PAUL CHAMBERS (b) “PHILLY” JOE JONES (ds)
1960
まだジャズを聴き始めたばかりの学生時代のある夏休み、郷里の日本楽器のレコード・コーナーで同い年のジャズ・ファン(慶大生)と知り合った。彼は高校時代からジャズを聴いていていろいろ教えてくれた。大のマイルス・ファンの彼が、ハバードでイチオシしたのが本作。まだ、‘BLUE SPIRITS’しか聴いたことのなかった僕は、あるジャズ喫茶に置いてある、というので早速行ってみた。そこは地元でも柄の悪さで知られた盛り場にあり、店の前に着くと、ちょうど与太った二人連れが出てきた。一瞬、気後れしたがヒョロの学生如きの命までは取られないだろうと中へ入った。そして、ハバードに脳天をぶち抜かれた。
その慶大生の彼とは、互いに帰郷した際、日本楽器で待ち合わせて一緒にジャズ喫茶へ行ったりしたが、卒業してからは、何時からとなく音信不通状態になった。それから数年後、ばったりとまた日本楽器のレコード・コーナーで再会したが、彼も親父が地元で大きな工場を経営していて、戻っていた。「最近、リスニング・ルームを改造したので聴きにおいで」と言うので訪ねてみた。資材倉庫を改築した20坪あまりの大きな部屋に‘ALTEC A7’がでーんと鎮座しており、更にビックリしたことに、床が刳り抜かれ床下からコンクリートのSP台が造られていた。アンプは定番のマッキンではなく、いろいろテストした結果一番合ったというデンオンの球でドライブしていた。
彼が最初に聴かせてくれたのは鳩でお馴染みのT・ジョーンズの‘April In Paris’(1572)。また驚いた。両SPの間のやや上の空間にジョーンズのtpがポッカリ浮いて聴こえるではないか。しかも柔らかくもエッジの利いたトーンで。SPから音が出ているのではなく、まるでそこにステージが有り、生演奏を聴いているようであった。そんじょそこらのジャズ喫茶が束になってかかっても敵わぬ程のいい音でした。家に帰って暫くは自分のあまりにもプアな装置と音でジャズを聴く気になれなかった。なお、その後、彼と会うこともなかった。今、どうしているのだろう?
デビュー2作目となる本作は、中隊長クラスともいえるモブレー、フィリーが加わり、更にパワーアップ。人気の1作目の‘OPEN SESAME’の影に隠れているが出来は甲乙付けがたい。一曲目の‘Asiatic
Raes’(ドーハムの蓮の花と同曲でロリンズのニュークス・タイムでも取り上げられている)から、ハバードのブリリアントなtpが全開、炸裂する。しかもメロディックに音を綴っている。そのメロディ・ラインは荒削りながら誰も真似できぬ唯一無二のものだった。
モブレー、フィリーが加わった分、前作よりハード・バップ色が強く聴こえるやもしれませんが、50年代とは明らかに違うハバードの新感覚のホーン・ワークが新しい時代の到来を高らかに宣言している。所々ミストーンや不安定なフレージングが散見するが恐れを知らぬ火の玉ペットが全てかき消している。
しかし、それだけではない。バラード曲‘I Wished I Knew’でみせる22才とは思えぬ腰の据わったプレイはどうだ!特にカデンツァ風のエンディング・ソロを聴けばA・ライオンがぞっこん惚れ込んだのも解るというもの。また、モブレーのソロも極上。
このマンハッタンの高層ビルを下から上へ撮ったジャケットとタイトルがライオンの高揚した心情を如実に表している。‘UP’の文字を更に二つ上に向かって重ねているのが何よりその証拠だ。この時、ライオン、ウルフ、マイルス、ゲルダー、そしてハバードの5人のベクトルは正しく一つ。
歴代の中、tpをもっともtpらしく吹いたのは、ハバードだけだった。
薄暗いジャズ喫茶の空間で、初めて聴いたあの記憶は、今も変わることはない。
(2004/1/23)
